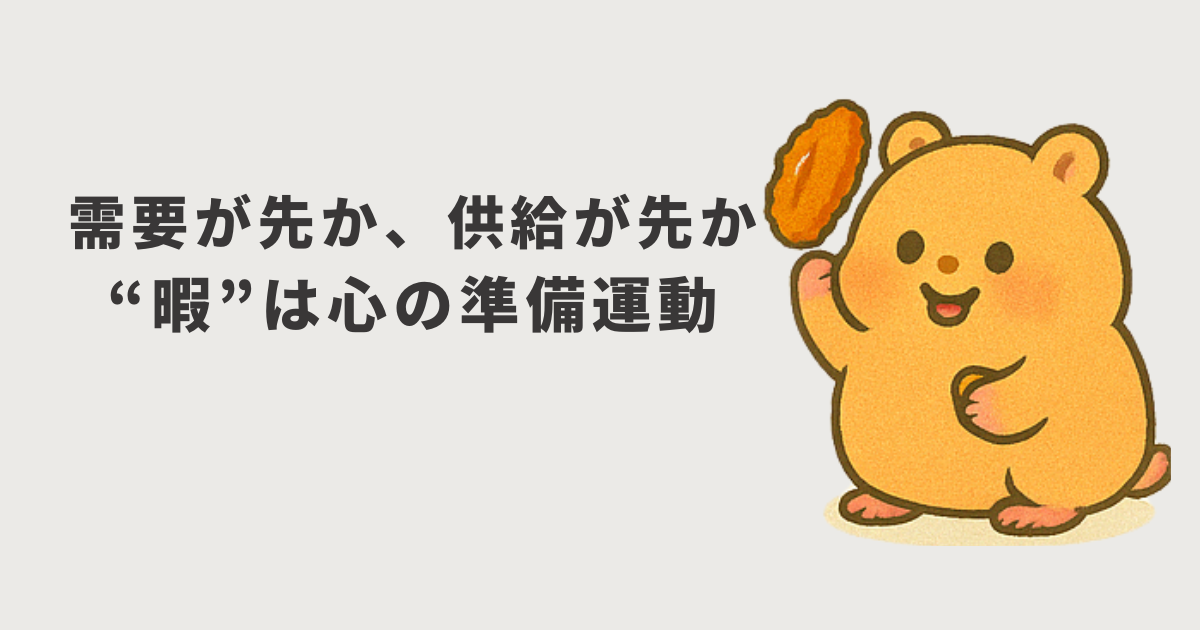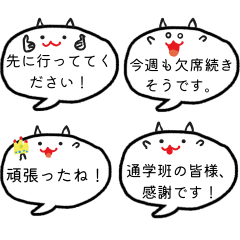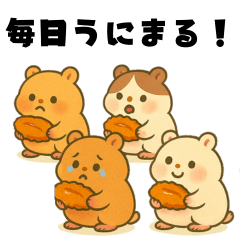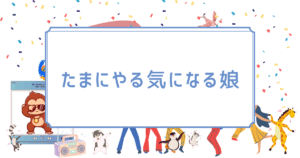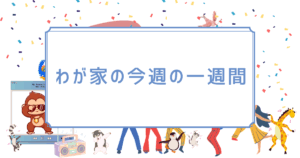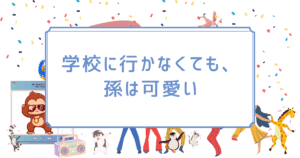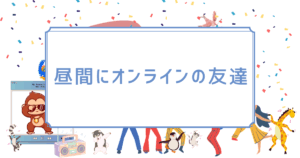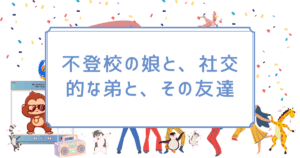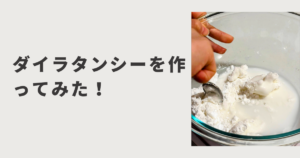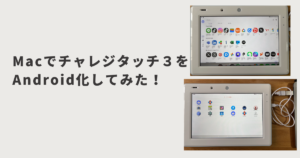やりたいことは、自分の中にある?外からくる?
不登校の娘が、よく口にする言葉があります。
「暇だな〜、なんかやることないかな」
YouTubeもゲームもやってるのに、また「暇」。次の暇つぶしを探してるけど、すぐ飽きてしまう。何か足りない。でもそれが何か、本人もわかってない感じ。
そんなある日、私自身が100均をうろうろしていた時に、ふと思ったことがあります。「何か欲しい」わけじゃないけど、面白そうなものがあれば買おうかな、っていうあの探し方。
これって娘の“暇だなー”と似てるかもしれない。
それってつまり、供給が先なのでは?
娘の「暇だ」、自分の「100均探し」。
どちらも、「やりたいこと」や「欲しいもの」が最初にあるわけじゃない。
なんとなく、外からくる”面白そうなもの”を待っている。面白そうなものがあれば、それに引っ張られて“やる気”が生まれるかも…と。そこでふと、疑問が湧きました。
そもそも本来、需要と供給って、どっちが先なんだろう?
原始時代は「需要が先」だったはず
考えてみると、原始時代の人間は「需要が先」だったはずです。
- お腹が空いた → 食べ物を探す
- 寒い → 火を起こす
- 危険 → 隠れる
欲求(需要)があって、それに応じて行動(供給)を生み出していたはずです。「必要は発明の母」という言葉の通りです。
現代は「供給が先」にあふれている
でも、今の私たちは違います。
- 広告
- SNSの「おすすめ」
- YouTubeの自動再生
- セールや新商品
- 100均やコンビニの陳列棚
まだ欲しいと思っていない人に、「これ欲しいでしょ?」と供給を差し出してくる。
それに反応して「なんか欲しくなってきたかも」と感じる。これはまさに、現代のマーケティングの基本的な仕組みです。
人類の脳の機能や構造は、原始時代から現代までほとんど変わっていないというのが定説です。つまり今は、
- 「需要→供給」の原始的な脳を持ちながら、
- 「供給→需要」の世界に生きている
もしかしたら、ここに、「満たされてるのに満たされない」という感覚の根っこがあるのかもしれません。
満たされてるのに、なぜか満たされない理由
スマホがあっても、動画があっても、ゲームがあっても、「なんかつまらない」「また暇」が起きてしまう。
これは、本当の“自分の欲求(需要)”が見えていないまま、供給に頼っているからなのかもしれません。
どれだけ選択肢があって、時間は潰せたとしても、「自分は何をしたいのか」がわからないと心は空っぽのまま。
勉強も同じ。需要がなければ動かない
これ、子どもの勉強にもまったく同じことが言えます。
- 「この問題やって」→やる気が出ない
- 「将来の役に立つよ」→ピンとこない
- 「みんなやってるよ」→他人事
こういうときも全部、供給が先になっています。
本人の中に“やりたい”や“知りたい”という需要がないまま、与えられても、心が動かないんです。
というか、これこそ今の教育の難しさかもしれません。
一方で、需要が先にあると学びは動き出す
逆に、「需要が先」にあるときは、人は驚くほど勝手に学びます。
- 「このゲーム、どうやって作るの?」→プログラミングに夢中
- 「もっと自由にお絵描きしたい」→デジタルツールに挑戦
- 「お小遣いを増やしたい」→計算やお金の知識に興味
このとき、勉強は「目的」ではなく「手段」になっている。
だから、本人の中から自然に「やってみよう」が生まれるんです。
親は供給者ではなく、“需要の探し人”に
「暇だなー」は、ただ時間を持て余しているだけじゃなくて、次の”やりたい”がまだ見つかっていないサインかもしれません。
そんなとき、私たち親はつい、「あれやってみたら、これやってみたら」と“供給”を差し出しがちです。でも、大事なのは「何がやりたいのか、一緒に探すパートナー」になっていくことなんだと思います。
「こんなの見つけたよ〜」「これ、自分だったらやってみたいかも」そんなふうに、選ばなくてもいい“ヒント”をそっと置いておくのがよいかもしれません。そうやって娘の中に眠っている“自分発の需要”が自然と芽生えるのを見守るのということが親ができることなのかもしれません。
暇は心の準備運動
選択肢もモノも情報もあふれている今の時代。気づけばいつも「供給」が先にあって、「これどう?」、「これ流行ってるよ」と次々と差し出され続けます。それは楽である反面、もしかしたら、供給に囲まれすぎて、自分の「やりたい」や「知りたい」がどこかに埋もれてしまってる、ちょっとした思考停止状態に陥っているのかもしれません。
そもそも人間の脳は、原始時代から「需要が先」の仕組みに慣れてきたはずなんです。だからきっと今も
いくら便利なものや楽しいものが外にあっても、「これがしたい」という自分の中の需要が先にないと“満たされてるはずなのに、どこか満たされない”という感覚になるんだと思います。
だからこそ、あえて立ち止まって、自分の中の“本当の需要”を探す時間を持ち、「自分は何をしたいのか」を見極める力が、大切なのだと思います。
これは、勉強も、遊びも、進路も、暮らしも、全部に通じる、“生きる力”につながる感覚です。
娘の「暇だなー」は、ただのヒマじゃなくて、何かが動き出す前の準備運動なのかもしれません。
全部「供給まかせ」ではなく、自分の「需要」を出発点にしていく。そんな生き方ができたら、きっと満たされた感覚に少しずつ近づけるんじゃないかと思っています。