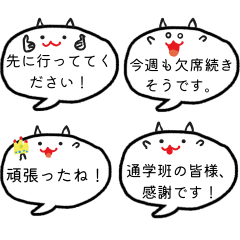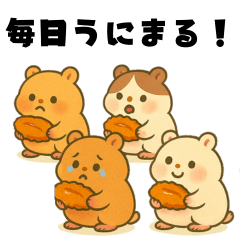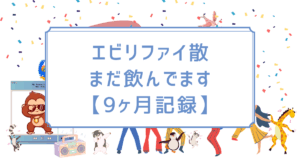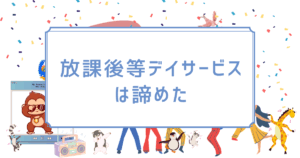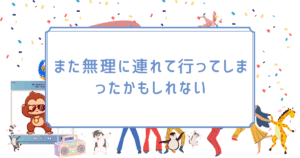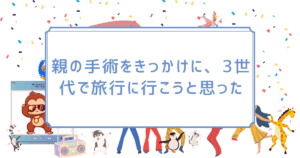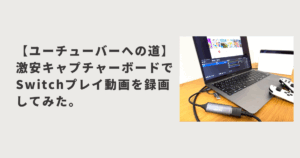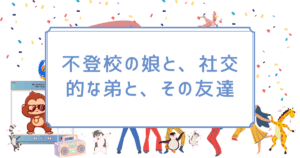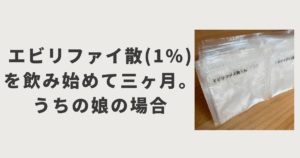まず最初に。この記事は、私自身と娘の体験をもとに書いた、私の頭の整理です。不登校の理由や状況はお子さん一人ひとり異なりますので、「こうするべき」という話ではありません。ただ、あの時の私たちのようのに悩んでいる方がいたら、「あ、こういうひともいるんだな」と思ってもらえたら嬉しいです。
最初は「どうしたらまた学校に行けるか」ばかり考えてた
娘が「学校に行きたくない」と言い始めたころ、私は毎日のように「どうしたらまた行けるようになるか」ばかり考えていました。
- 「今日は給食、好きなメニューだよ?」
- 「今日は体育あるよ」
- 「友達、待ってるかもしれないよ?」
- 「ちょっとだけでも行ってみようか?」
- 「大丈夫。行けば楽しいこともあるよ」
とにかく、なんとか学校に戻ってほしくて、あの手この手で誘導していました。
それが愛情だと思っていました。
でも今思えば、それって全部“子どもの不安”をなんとかするための言葉じゃなくて、“親である私の不安”をなんとかするための言葉だったと思います。
親として導かなきゃと思っていた
正直、子供が不登校になるとは想像もしていませんでした。どう対応するのが正解なのかもわからず、焦っていました。不登校関連のことをインターネットで調べたり本を読んだり。でも、不登校にはマニュアルも近道もないし、「これが正しい」というものもありません。
それでも「学校に行くのが当たり前」「行かないのは問題」という前提が無自覚に私の中にも深く根を張っていました。そのため、行け泣きながら「行きたくない」と言う娘を前にして、私は「親なんだから、しっかりしなきゃ」と思っていました。
- 「大丈夫、行けば楽しいこともあるよ」
- 「今日はちょっとだけ頑張ってみようか」
そう声をかけることで、“愛情”や“励まし”を伝えているつもりでした。
「登校できた」はゴールじゃなかった
不登校になって間もない頃に、私が強く背中を押してなんとか朝の会だけ教室の椅子に座らせたことがありました。「教室に入ればなんとかなるから!」と声をかけて。少し強めに背中を押しました。多少厳しくてもそれも”愛情”という思いでした。娘は渋々椅子に座り、なんとか朝の会の間は教室にいることができました。先生からも「今日は教室に入れてよかったですね」と言ってもらえました。
でも、帰り道、娘はどっと疲れた様子。そして次の日からは、それまで以上に動けなくなってしまいました。
その日、「椅子に座れた」という“結果”だけを見て、私はつい安心してしまいました。でも、本人の気持ちが置いてきぼりになっていたら、それは「できた」とは言えないんだと思います。
無理やりやらせてできたことは、次につながらない。むしろ「つらさを我慢した記憶」として残ってしまうこともある。
私が本当に望んでいたのは、「学校に行くこと」そのものじゃなくて、「安心して毎日を過ごせるようになること」だったはず。そう気づいたとき、ようやく私は「行かせる」より「寄り添う」を選べるようになってきました。
- 子どもの不安に寄り添うこと。
- 泣き声を否定せずに聴くこと。
- 何もできない自分を責めすぎないこと。
- 未来を心配しすぎず、今日を一緒に生きること。
不登校は、親としての自分を見つめ直す時間でもあった気がします。
今、あの頃の自分に声をかけるなら
- 「無理に元に戻そうとしなくていいよ」
- 「ちゃんと向き合おうとしてるだけで、十分がんばってるよ」
- 「今は“できること”より、“一緒にいること”の方が大事だよ」
そんなふうに、当時の自分に声をかけてあげたいと思います。