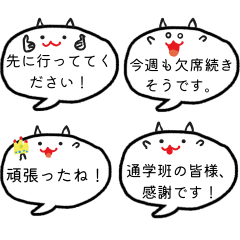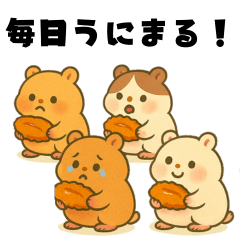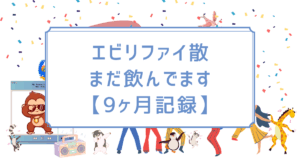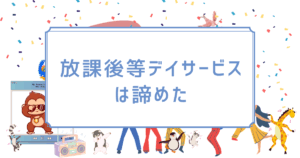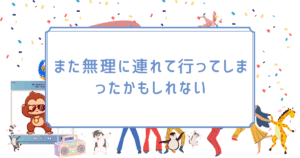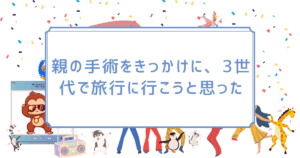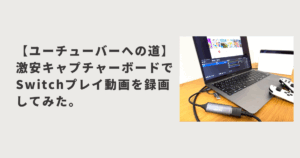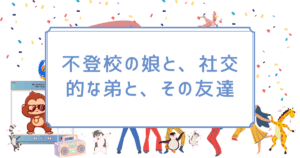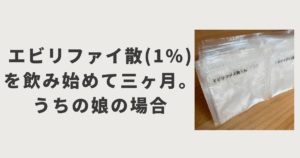──娘が「明日が来るのが嫌だ」と泣いた日曜日の夕方。あの日のことは、今でもはっきりと覚えています。
幼稚園の頃からの行き渋り
娘には、幼稚園のころから“行き渋り”の傾向がありました。朝の支度に時間がかかり、「お腹が痛い」と泣いた日もありました。でも、なんとか登園させれば、帰ってきたときには笑顔で「今日は◯◯ちゃんと遊んだよ」と話してくれていました。
小学校に上がってからもその傾向は続きました。行く前は毎朝のように渋り、でも行けばそれなりに楽しめている様子。私たち親も、「朝が苦手なタイプなんだろう」と軽く捉えていたところがありました。
「明日が来るのが嫌だ」と泣いた日曜日
それが、2年生になった頃から少しずつ変わっていきました。
「体調が悪い」「お腹が痛い」「頭が痛い」──そう言って学校を休むことが増えていきました。でも、休むと決めたとたん、急に元気になる。最初は正直、「ズル休みなのでは?」と思ってしまい、「ほんとは元気なんじゃないの?」なんて嫌味を言ってしまったこともありました。
ただ、次第に日曜日の夜になると機嫌が悪くなり、月曜日のことを思い出して不安そうな表情を見せるようになりました。そしてついに、あの日──日曜の夕方、娘はぽろぽろと涙をこぼしながら言ったのです。
「明日が来るのが嫌だ」と。
その言葉を聞いて、私はようやく気づきました。
これは単なる“ズル休み”じゃない。娘は、自分なりに毎日がんばっていたんだ。「学校に行く」ということが、娘にとっては大きな負担で、心のエネルギーをすり減らしながら過ごしていたのだと、あの涙を見てやっと理解できました。学校に行くことそのものが、娘にとっては本当にしんどいことだったのだと。
同伴登校の日々と、親子ともにすり減った時間
それでも、学校とのつながりを切ってしまうのが怖くて、私たちは“同伴登校”を始めました。手を引いて一緒に学校まで歩き、教室に送り届ける。
最初のうちはなんとか登校できていたものの、すぐに教室には入れなくなり、私と一緒に廊下で授業の声を聞くだけの日が続くようになりました。それでも「来ていることに意味がある」と自分に言い聞かせ、毎朝手を引いて学校に向かっていました。
けれど、次第に登校の途中で泣き出し、立ち止まって動けなくなることが増えてきました。そんな朝が続いたある日、道端で泣く娘を無理やり引っ張りながら、
「自分はいったい何をしているんだろう」
と、ふと我に返ったことを覚えています
これって、本当に娘のためになっているのか?こんなことを続けても、かえって学校が嫌になるだけじゃないか?
それでも、「学校との関係が完全に途切れてしまってはいけない」と思い込み、せめて挨拶だけでも……と毎朝一緒に行く日々を続けました。
そうやって、なんだかんだで半年ほど、無理を重ねていたと思います。
疲弊していたのは、娘だけじゃなかった
その頃が、もしかしたら親子ともに一番疲れ切っていた時期だったかもしれません。
私は仕事をフレックスで調整できていたため、何とか回してはいたものの、毎朝の送り迎え、途中で泣き出す娘の対応、学校とのやりとり──心も体もすり減っていきました。仕事に集中できない日も増え、次の日のことを考えて夜に眠れなくなることもありました。
娘の不安と、自分の焦りと、社会の「普通」に取り残されていくような感覚。いろんな感情が重なって、私も限界が近かったように思います。
今振り返って思うこと
今振り返ると、あのときの私は「学校に行かなきゃ」という気持ちにとらわれすぎていたのかもしれません。「学校に行くのが当たり前」という前提の中で、娘のSOSに気づきながらも、真正面から受け止めきれていなかったのです。
「明日が来るのが嫌だ」と泣いたあの日曜日の夕方の空気と、娘の涙の温度だけは、今もずっと心に残っています。
無理に引っ張ることではなく、娘の気持ちに寄り添い、一緒に考えていくこと。そして、娘が安心して自分らしくいられる場所を、少しずつ一緒につくっていくこと。
これからも、私は学び続けたいと思っています。